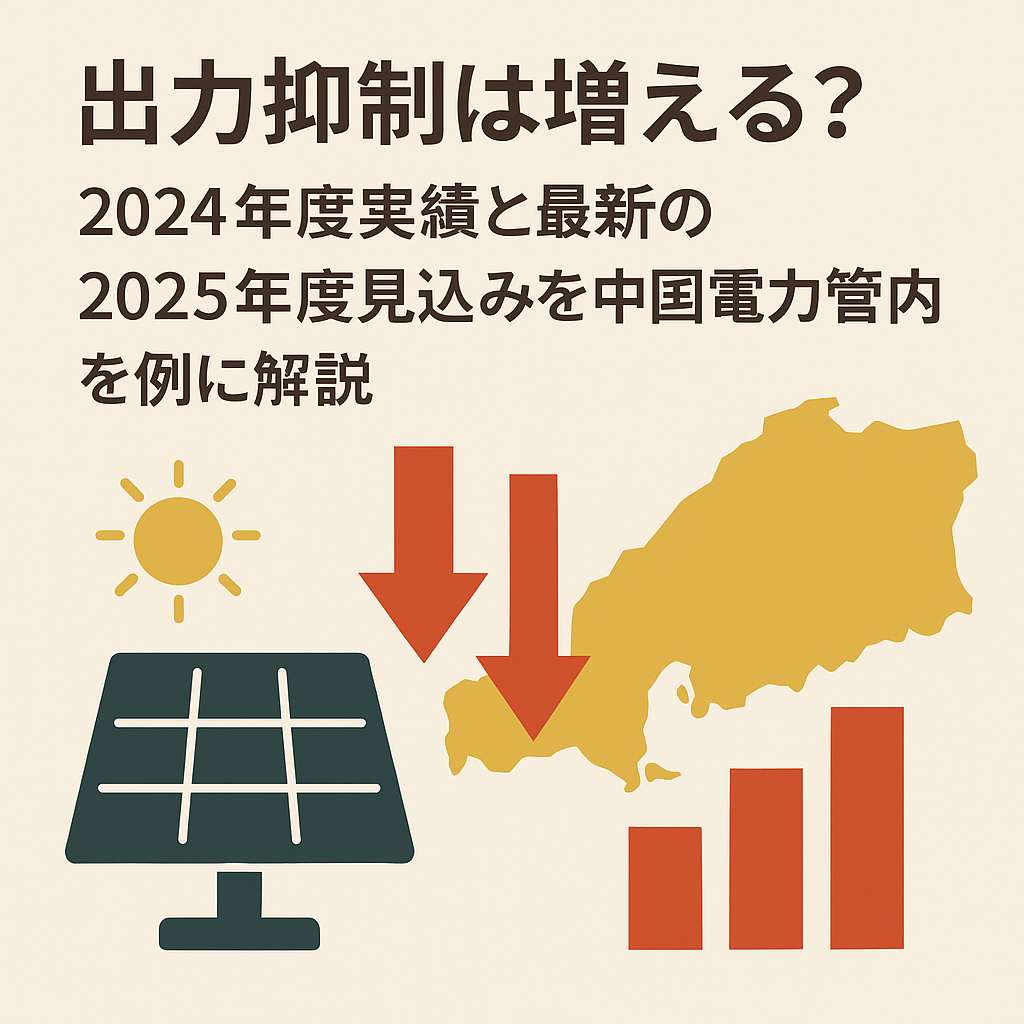近年、太陽光発電の出力抑制が各地で実施されており、出力抑制率は高いままで推移しています。FIT事業者は再エネ特措法に基づき出力抑制を拒否できません。多くの事業者がFIT事業者認定されているため、出力抑制率が高いと多くの事業者の売電収入が大きく減少し、大きな課題です。
そこで、この記事では、太陽光発電における出力抑制の最新動向について詳しく解説します。特に中国電力管内における出力抑制の2024年度実績や2025年度最新見込みを例にとり、今後の動向を解説します。また、今さら聞けない出力抑制の基礎知識もまとめました。売電収入の減収に悩む事業者様、出力抑制を改めて理解し、出力抑制の最新情報を2025年度の太陽光発電所の経営にお役立てください。
2025年度の出力抑制は?
近年、「出力抑制」ということばを耳にすることが増えました。「出力抑制」は、簡単にいうと、電力会社が太陽光発電所の発電を一時的に制限することです。当然のことながら、発電を制限されてしまうと、太陽光発電事業者の売電による収入が減ってしまいます。ここでは、全国における出力抑制の傾向と、太陽光発電に向いているといわれている中国地方を管轄する中国電力管内のデータを見てみましょう。
全国に広がる出力抑制
出力抑制は、実際にはどのように広がっているのでしょうか。2025年1月23日資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御に関する短期見通し等について」によると、年々実施範囲が徐々に拡大されてることが分かります。実施年度と実施エリアとの関係を以下の図に示します。
参考:2025年1月23日資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御に関する短期見通し等について」(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/smart_power_grid_wg/pdf/001_02_01.pdf)
図を見てわかるように、2022年度からは北海道、東北、四国や中国、沖縄の各エリアで実施されました。2024年度には中部、北陸、関西でも実施され、東京電力を除く国内のほぼ全域で実施されたこととなります。そして、2025年度には東京電力でも出力抑制を実施する見込みです。
つまり、2025年度は出力抑制がどの地方でも要請される見込みで、どの地方の太陽光発電所の事業者も売電収入が減少する可能性があります。
中国電力管内の出力抑制の推移
中国電力管内となる中国地域は、鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県の5つの県で構成されています。
中国地域の瀬戸内海側は温暖な気候で日照時間も長く、太陽光発電に適している地域だといわれています。中国電力グループ統合報告書2024(https://www.energia.co.jp/ir/irzaimu/pdf/tougou/tougou_05.pdf)
によると、中国地域の太陽光発電電力の対全国シェアは12%だそうです。すなわち、太陽光発電に適しており、それなりの全国シェアも持つ中国電力管内の出力抑制の推移は重要な指標と言えるでしょう。
参考:2024年3月11日 経済産業省 資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの出力制御の抑制に向けた取組等について」(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_01_00.pdf )
2024年9月18日 中国電力ネットワーク株式会社「2024年度の再エネ出力制御の見通しについて」(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/052_s02_06.pdf )
表を見てわかるように、中国電力管内の2023年度の出力抑制率は3.6%です。これに対し、中国電力管内で初めて出力抑制が実施された2022年度は0.45%です。すなわち、1年で出力抑制率は8倍にもなったことが分かります。さらには、2024年度はさらに出力抑制率(見通し)が上昇し、高い水準で推移しています。
なお、2024年度においては、「67回」もの出力抑制が実施され、日ごと最大出力抑制率は「33.79%」、最大出力抑制量は「2,348MWh」となっております。
つまり、太陽光発電所の事業者としては、本来得られるはずの売電収入が大きく減っているといえるでしょう。
中国電力管内の2025年度の出力抑制予定は?
中国電力ネットワーク株式会社の「2025年度の再エネ出力制御の見通しについて」によると、2025年度の出力抑制見込みは、太陽光・風力合わせて2.82%で2.75億kWh、太陽光発電は2.99%とされています。
すなわち、2025年度も2024年度と変わらず高い水準で出力抑制が実施される見込みです。
参考:2025年1月23日中国電力ネットワーク株式会社「2025年度の再エネ出力制御の見通しについて」(https://www.energia.co.jp/nw/energy/kaitori/control/pdf/seigyo_03.pdf)
今さら聞けない出力抑制
ここまで、全国で出力抑制が実施されていること、太陽光発電に好適とされている中国電力管轄内の出力抑制の推移、2025年度の出力抑制見込みについて解説しました。
「出力抑制」は売電収入の低下につながることはお分かり頂けたと思います。ここで、「出力抑制」について、今一度整理してみましょう。
太陽光発電の出力抑制とは、最初に申し上げたように、簡単にいうと電力会社が太陽光発電所の発電を一時的に制限することです。発電を制限されると、当然のことながら太陽光発電事業者の売電による収入は減ります。
太陽光発電所の多くの事業者は、残念ながら出力抑制を拒否できません。ただし、出力抑制での減収を救済するための補償ルールはあります。
この章では、太陽光発電の出力抑制について解説し、この制度ができた背景と仕組み、事業者への補償ルールについて解説します。
出力抑制はなぜ必要?
出力抑制が必要な理由は、電力の需要と供給が「同時同量」の原則で管理されているためです。「同時同量」とは、電気の供給量(発電量)と電気の需要(消費量)が同じ時に同じ量になっていなくてはならないということです。
産業や生活を安定して営むためには、電力システムの安定した稼働が必要になります。もし、電力システムが不安定になると産業や人々の生活に様々な支障が生じるのは明らかです。
もし、「同時同量」で管理されている電力の需要と供給のバランスが崩れると、電力システムが不安定になります。特に電力の供給過多が起こると、電力網の電圧および周波数に異常が起こりやすくなります。その結果、電子機器の故障あるいは自動停止が頻繁に起こる可能性があり、事態は深刻です。
さらには、安全装置が発動して発電所の停止につながりかねません。これにより、予測不能な大規模停電を招く可能性もあります。2018年9月の北海道全域のブラックアウトは、電力の需要供給バランスが崩れたために起こりました。
このような事態を避けるために出力抑制が必要です。
出力抑制は断れない?
電力の需要供給バランスを保つための出力抑制は太陽光発電だけでなく、火力発電(ガス、石炭、石油)やバイオマス発電などでも行われています。出力抑制が要請される場合、順番があります。
引用:経済産業省 資源エネルギー庁 エネこれ「再エネの発電量を抑える「出力制御」、より多くの再エネを導入するために」(https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kyushu_syuturyokuseigyo.html)
図に示すように、最初に出力抑制されるのは、火力発電です。同時に、揚水水力発電の調整も実施されます。続いて、他地域への電力送電(連係線利用)が実施され、さらにバイオマス発電の出力調整と順番に出力抑制が実施されるのです。
それでも発電を抑えなければならない場合は、太陽光発電および風力発電の出力抑制が要請されます。
なお、出力抑制は出力制御とも称されます。
太陽光発電の出力抑制の順位は低いものの、近年は多く出力抑制が実施されているのが実情です。これだけ順位が低いのだから断ってもいいと思う方も多いでしょう。しかし、残念ながら、出力抑制は断れません。
これは、FIT事業者は出力制御の要請には法的に従う義務があると再エネ特措法で決められているためです。FIT事業者として認定し続けてもらうためには、義務を順守しなくてはなりません。
2021年3月以前に電力受給契約の申込みを終えていて、FITの事業計画認定を受けている事業者には、出力規模や設置場所、さらに電力受給契約の申込み日或いは締結日に基づいて3つの補償ルールのうちのいずれかが適用されます。なお、3つの補償ルールは以下の通りです。
- 旧ルール
- 新ルール
- 無制限・無補償ルール(指定ルール)
FIT以外の太陽光発電所は無制限・無補償ルールになります。補償ルールについては、のちほど解説します。
2021年4月以降に新たに一般送配電事業者と電力受給契約の申込みを行っており、太陽光発電所を建設する事業者の場合は、「3.無制限・無補償ルール」が適用されます。このルールに基づいて出力抑制に応じなければなりません。
補償ルールとは?
補償ルールとは、出力抑制により売電収益が減収する太陽光発電事業者に対して補償をおこなうものです。ただし、FIT事業者以外の太陽光発電所はいずれも無制限・無補償ルールの対象になります。
補償ルールは以下の3種類です。
- 旧ルール(30日ルール)
- 新ルール(360時間ルール)
- 無制限無補償ルール(指定ルール)
順番に解説します。
旧ルール(30日ルール)
旧ルール(30日ルール)は、年間の出力制御日数が30日を超える場合に適用されるルールです。30日目までは出力抑制に応じても補償はなく、31日目以降から補償されます。
新ルール(360時間ルール)
2015年にFIT制度(固定価格買取制度)が改定されたことに伴い、「360時間ルール」が新たに導入されました。旧ルール(30日ルール)と大きく異なるのは補償を時間でカウントすることです。
旧ルール(30日ルール)では、その日のうちに何時間出力抑制があったかに関わらず出力抑制があれば1日としてカウントしていました。一方、新ルール(360時間ルール)では、時間単位でカウントされるため、運用の精度が高まりました。
無制限無補償ルール(指定ルール)
無制限無補償ルール(指定ルール)は、先ほどの新ルール(360時間ルール)の後に制定されたものです。出力抑制に対する補償はありません。つまり、出力抑制に応じても全く補償はありません。
補償ルールについての注意
補償ルールについては注意点があります。太陽光発電所の設置地域によって管轄電力会社は異なります。設置地域を管轄する電力会社ごとに補償ルールの適用範囲が異なる点には注意が必要です。
管轄する電力会社によって、各補償ルールに対応する接続申込日、出力規模が異なります。そのため、同じ条件でも管轄する電力会社によって補償の内容が変わることがあります。この点には注意が必要です。
例えば、今回取り上げている中国電力管内配下の通りです。
- 2015年1月25日まで:旧ルール
- 2015年1月26日から2018年7月11日まで:新ルール
- 2018年7月12日以降:無制限・無補償ルール
出力抑制が増える理由
断ることができない出力抑制は、今後、全国的に増加する傾向です。その年の気候や太陽光発電所の数の増加によっても出力抑制は増加しますが、以下のような理由でも増加します。
1.節電意識の高まり
2.再エネの増加
3.他地域への送電量の減少
順番に解説します。
節電意識の高まり
近年の電気料金の高騰により企業や個人の節電への意識が高まっています。特にウクライナ情勢の影響は深刻です。電気料金は益々高騰しており、企業や個人の電力需要の減少が起きています。
「同時同量」で管理されている電力の供給と需要において、節電意識の高まりから需要が減れば当然のことながら必要な供給量が減ります。このことから、出力抑制の量および機会の増加は必須です。
再エネの増加
今や世界規模で再生可能エネルギーが取り入れられています。日本では、東日本大震災を契機に脱原発の動きが加速しました。さらにはカーボンニュートラルも進められています。
このような時代背景もあり、各地で太陽光発電を含む再生可能エネルギーの導入が増えてきました。つまり、太陽光発電所などが増え、発電可能な総発電量が多くなっています。
電力は「同時同量」で管理されているため、電力需要が多くバランスがとれている時は問題ありません。しかし、ゴールデンウィークのように長期で産業が休止するような場合には電力需要が低くなり、発電量が過多になってしまいます。太陽光発電所の増加により発電可能な総発電量が増えれば、この傾向が強くなっていきます。そこで、全国的な出力制御が実施されるようになりました。
他地域への送電量の減少
先ほど申し上げたように、出力抑制には順番があります。1番目の火力発電および揚水水力発電の調整は実施可能です。しかしながら、近年では2番目の他地域への送電による出力抑制が困難となっています。
これは、各地域においてある程度の電力を確保できるようになり、需要が低いときにはどの地域でも他の地域からの送電を必要としないからです。結果として、2番目の他地域への送電による出力抑制が困難となり、3番目の太陽光発電や風力発電の出力抑制の量が増加しています。
2025年度出力抑制が減ることはない見込み
これまで述べた3つの理由が急に解消することはありません。そして、全国において同じ傾向が見られます。すなわち、2025年度において全国的に出力抑制が減ることはないといえます。
【2025年度】出力抑制は全国的に高い水準で推移
これまで述べたように、中国電力の管轄以外の地域でも出力抑制が広まっています。2025年度には、出力抑制は全国で実施される予定です。
その上、先ほどの章で解説したように、「1.節電意識の高まり」「2.再エネの増加」「3.他地域への送電量の減少」が解消することはなく、2025年度の中国電力の管轄内の出力抑制も高い水準で推移しています。他の地域でも同様で、全国的に出力抑制が増える傾向が続くといえます。
従って、2025年度は、出力抑制が全国的に高い水準で推移するでしょう。
太陽光発電事業者が受ける影響
2025年度も出力抑制が全国的に高い水準で推移するため、太陽光発電事業者の売電による収益が大きく減ってしまう傾向にあります。この傾向は、情勢を鑑みると当分続くといえるでしょう。
出力抑制による減収を少しでも減らすには、出力抑制を自動(オンライン)で制御できるシステムを導入する必要があります。オンラインで遠隔制御できる太陽光発電所のメリットは、現地に人員が赴いて制御するオフラインの太陽光発電所よりも出力抑制量を低減できることです。
ただし、2015年1月26日以降に接続申し込みした太陽光発電所では、このシステムの導入が義務化されています。これは、先ほどの補償ルールの項で述べた360時間ルール(新ルール)が適用されている太陽光発電所にあたります。
それ以前の太陽光発電所、先ほどの補償ルールの項で述べた30日ルール(旧ルール)が適用されている太陽光発電所には設置義務がありませんでした。このような太陽光発電所がシステムを導入する場合の機器を追加設置する費用は、太陽光発電所の事業者が負担しなくてはなりません。
2021年11月12日一般社団法人太陽光発電協会「太陽光発電のオンライン制御化に向けた課題」(https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/033_03_00.pdf)では、30日ルール(旧ルール)が適用されている太陽光発電所がオンライン制御に対応するための初期費用の推定目安が挙げられています。
- 高圧の設備においてはおよそ200万円~600万円
- 特別高圧の設備に2000万円~4000万円程度
太陽光発電所の事業者にとっては大きな出費であり、出力抑制で売電収入が減少する事業者にとっては大きな影響です。
太陽光発電所にはパワコン交換時期を迎え、支出が大きくなる事業者もいるでしょう。2012年にスタートした産業用太陽光発電の全量売電制度(FIT制度)を利用して、多くの産業用太陽光発電所が事業を開始しました。2024年には、これら多くの産業用太陽光発電所が11年目を迎え、パワコンの交換時期となります。パワコンの交換で費用が掛かるうえに出力抑制で売電収入が減少するのは、事業者にとっては大きな痛手です。
FITの期間は、住宅用太陽光発電(出力10kW未満)の場合は10年間、事業者が設置する産業用太陽光発電(出力10kW以上)の場合は20年間です。FIT期間が終了した後は、新たな契約などを結んで事業を続けることとなります。この場合、FIT期間と同様の売電収入が得られるとは限りません。このような事業者にとって、出力抑制のために売電収入が減収するのは大きな問題です。
出力抑制により売電収入が減ることは、太陽光発電所の事業者にこのように大きな影響を及ぼします。収支のバランスによっては、事業を続けるかどうか悩む事業者もいるでしょう。
売電収入の減少にお悩みなら売却を検討しませんか?
売電収入の減少にお悩みの太陽光発電所の事業者様、売却を検討してみませんか?
全国的に行われる高水準の出力抑制をはじめ、施設のオンライン化、パワコンの交換、FITの終了など、売電収入の減少を起こす要因は多くあります。また、太陽光発電所は年数が経てば経つほど修繕などにもコストがかかり、売却価格が下落する可能性もあります。
売電収入が減少する上に売却価格も下落してしまうと、あなたのトータルの収入が大きく下がってしまう可能性があるのです。
そのようなお悩みを持つ方、ぜひ売却をご検討ください。
太陽光発電の売却ならプレグリップエナジーがおすすめ
太陽光発電を売却するのであれば、プレグリップエナジーがおすすめです。プレグリップエナジーは太陽光発電のあらゆるフェーズに精通しており、安心してお任せいただけます。
すぐに売却を希望される場合は買取サービス、できるだけ高額での売却を希望される場合は仲介サービスのご案内が可能です。買取サービスの場合は、お問い合わせから売却まで最短1週間で対応させていただきます。
太陽光発電の売却を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
中国電力管内以外の地域にも出力抑制は広がっています。2025年度にはすべての電力会社管内で実施される見込みです。
再エネ特措法によりFIT事業者は出力抑制を拒否することはできません。そのため、多くの事業者が出力抑制により売電収入の減少を余儀なくされるでしょう。
しかも、これまで解説したように2025年度も高い水準で出力抑制が要請されることは明らかです。どの地方の太陽光発電所においても出力抑制による売電収入の減収は避けられません。
出力抑制による減収を減らす方法としては、システム化の装置を追加設置することも考えられます。しかしながら、設置費用は事業者が負担しなくてはなりません。出力抑制の減収と設備の費用で事業者への影響は非常に大きなものとなります。
事業者の中にはパワコンの交換時期を迎える事業者やFIT期間が終了する事業者もいるでしょう。このような事業者にとっては、出力抑制による減収は深刻な問題です。
このような影響を受ける事業者様、一度売却を検討してみてはいかがでしょう?事業者様が直接売却をするのは大変です。そこで、買取に精通した買取業者に相談してみるのもひとつの手です。
プレグリップエナジーは、太陽光発電のあらゆるフェーズに精通しており、安心してお任せいただける企業です。ホームページではチャットによる買取事例のご案内も行っています。太陽光発電の売却をご検討の方、ぜひお気軽にお問合せ下さい。